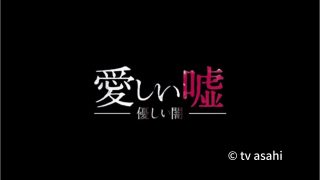年表で整理
平家は負けっ放しではない
- STEP011181. 1南都焼討大仏が焼かれる(平家勝利)
- STEP021181. 2平清盛・没びわ平家を追い出される
- STEP031181. 2城 資永・没木曾義仲攻め中止
- STEP041181. 3墨俣川の戦い平重衡・維盛軍が源行家軍を破る(平家勝利)
- STEP051181. 6横田河原の戦い木曾義仲、越後の平家軍を破り大勢力に(源氏勝利)
- STEP061181. 8養和の北陸出兵平家の北陸征討が失敗(源氏勝利)
- STEP071181.8~1182.4鎮西平定平貞能が1年がかりで九州の乱を鎮圧(平家勝利)
- STEP08平家身動き取れず
- STEP091183. 4火打城の戦い平家が10万の大軍(総大将維盛)で北陸討伐へ。越前・加賀を奪い返す
- STEP101183. 5般若野の戦い平家の北陸遠征先遣隊と木曽義仲の先遣隊が越中で激突。敗れた平家は加賀と越中の国境で足踏み(源氏勝利)
- STEP111183. 5倶利伽羅峠の戦い狭い山で奇襲・夜襲を受け平家北陸遠征軍本隊が総崩れ。逃げ道なく地獄谷に転落して7万騎が壊滅(源氏勝利)
- STEP121183. 6篠原の戦い平家北陸遠征軍別動隊が木曾義仲軍に敗れる(源氏勝利)
- STEP131183. 7平家・都落ち後白河法皇が比叡山に逃亡。安徳天皇と三種の神器を持って平家都落ち
- STEP141183. 7木曾義仲が京に入る木曾義仲軍、統制なく京で狼藉を働く。京の治安は悪化
- STEP151184. 1木曾義仲が粟津で戦死木曾義仲、鎌倉の頼朝軍に敗れ討死
スポンサーリンク
びわ越後へ
越後に居るらしいという情報を得て、びわは越後を目指す
墨俣川の戦い
「墨俣川の戦い」の概要
尾張・三河で独自の勢力を築いた源行家(頼朝の叔父:以仁王の挙兵の黒幕)が、平家打倒の挙兵をした軍と、それを討伐する平家軍(大将は平重衡)が美濃(今の岐阜県)で戦った。頼朝は異母弟の源義円を援軍として送っていた。
→ 平家軍の圧勝
頼朝の異母弟源義円が討ち死に。
 負けてガックリする頼朝を北条政子が叱咤する
負けてガックリする頼朝を北条政子が叱咤する
また、源行家が鎌倉に逃げ込み、頼朝に助力を要請しますが、頼朝は拒否。源行家は木曽義仲を頼って信濃に逃げ延びます。
スポンサーリンク
木曾義仲起つ
平家打倒を決意
 ハンモックで寝転ぶ義仲。野生や自由人ぶりを表現
ハンモックで寝転ぶ義仲。野生や自由人ぶりを表現
 木漏れ日から射す陽。義仲が陽の当たる場所に出る事を表わす
木漏れ日から射す陽。義仲が陽の当たる場所に出る事を表わす
びわ、再び京へ
城資永の室であったが、城資永が没した為、京に舞い戻ったとの事

城資永は、都にいた事もあり、清盛の信頼も厚かった
横田河原の戦い
この時、木曾義仲の別働隊は平家の赤旗で城軍の近くまで行き、近づいた後、源氏の白旗に持ち替えて、怒涛の攻撃をします。そのタイミングで木曾義仲の本軍も突進。城軍は混乱の中、敗走します。
木曽義仲、一大勢力に!
スポンサーリンク
命運を分けた北陸決戦
火打城の戦い
初戦は越前(福井県)の火打城。5000の兵で立て籠る源氏軍だが、平家の大軍に恐れをなした内通者が出て、あっさり平家方維盛軍の勝利。尚、この時、木曾義仲は越後にいた。
維盛率いる平家軍はこのまま加賀(石川県)を制圧、越中(富山県)との境にまで進出する。
般若野の戦い
<平家方維盛軍の思惑>
木曾義仲軍が親不知(越後・越中の国境)を超えて、越中に進軍する前に親不知(当時は寒原)に兵を派遣する。越中前司平盛俊に兵5,000を与えて先遣隊とする。
<木曾義仲の思惑>
平家より先に越中に入り迎え撃つ。今井兼平に6000の兵を与えて先遣隊とする。
先を越された、平盛俊は般若野に陣取る。夕方、平家軍が動かないと見ると、今井兼平は、意表をつく夜襲を実行。平家軍は敗走して、加賀との国境の俱利伽羅峠まで後退する。木曾義仲本軍は、今井兼平軍と合流。俱利伽羅峠まで進軍する。
このときの侍大将である平盛俊は平宗盛の家人。重盛の一門(小松一門)とは、手柄を争い合う仲で、意思疎通や経験の共有が出来ていなかった可能性がある(「玉葉」より)
平維盛軍、木曽義仲軍、両軍の進路

俱利伽羅峠の戦い

<平家方維盛軍の思惑>
軍勢は多いので広い場所で戦いたい。砺波山を越えて広い砺波平野に入りたい。
<木曾義仲の思惑>
砺波山を降りさせてはならない
平家軍の背後に兵を回らせて、取り囲んだ木曾義仲軍は、夜襲をかける。

(今井兼平)巧く行ったじゃねえか
(巴御前)一万騎もの兵を背後に動かすとは
(木曾義仲)礼儀正しい奴らには思い付かない戦法だよな
両軍布陣図

スポンサーリンク
囲まれた平家軍は混乱して、唯一敵がいない場所に逃げようとするが、そこは谷で7万騎が谷に落ちる。
 火牛の計の描写
火牛の計の描写
 泣きながら敗走する維盛
泣きながら敗走する維盛
木曾義仲が寡兵で大軍を破ってきたのは、夜襲や奇襲。それなのに、またしても夜襲・奇襲にやられる
篠原の戦い
ここは、正々堂々の戦いであったが、勢いは木曾義仲軍にあり、平家軍はここでも敗れて敗走する。
斎藤実盛は実は、木曾義仲の命の恩人であった。
むざんやな 甲(かぶと)の下の きりぎりす
平家、都落ち
徳子と安徳天皇

天皇と三種の神器を携えて都を落ち、福原へと向かう

(徳子)妻や子供を残していくものが多いそうよ
(資盛)京が源氏の都になるというのに
(徳子)いいえ、帝がいらっしゃるところが都よ

維盛
 自分のせいで、と涙する維盛
自分のせいで、と涙する維盛
福原落ち
安徳天皇行幸一行、平家一門は、福原に落ちますが、福原も都を遷してから3年が経っており、荒れ果てていた

福原で一夜を明かしたのち、焼き払って、大宰府を目指して出港する

九州の反乱を鎮定した平貞能(小松一門)が、兵を引き連れて帰京したが、その数は一千騎あまり。大軍を期待した平家の面々は失望したという。
平貞能は、都落ちしても平家が落ち着ける場所は無いと主張して都に残り、平重盛の墓が荒らされるぬように、掘り起こして、高野山に移したといわれている。
平家なき都へ



 さて、誰でしょう?
さて、誰でしょう?