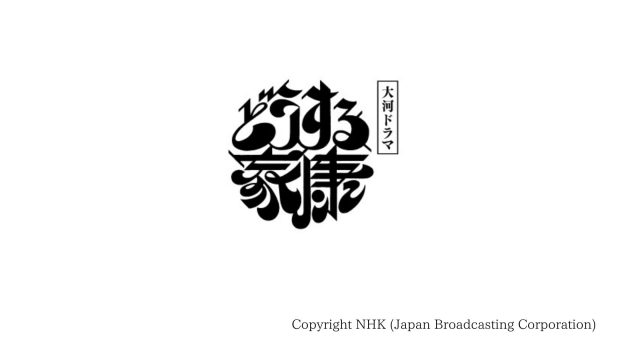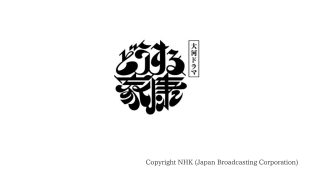女城主・お田鶴
スポンサーリンク
お田鶴の最期
お田鶴の最期は、幾つかの史料通りでした。
- 侍女十数人を左右に随え敵陣に切り込み討死
- 緋威の鎧を着用
(『徳川伝記』『井伊家伝記』『改正三河後風土記』『武家名目抄』『東海道五十三次:附・名数雑談』『概説静岡県史』など)
吉田松陰(『辛亥歳雜抄』にて)などが、お田鶴を激賞していますね。武勇と志操を高く評価する史料は多く、お田鶴は地元の領民たちにも慕われていたようです。それを打ち果たした家康は遠江では、しばらく居心地が悪かったかもしれません。
とこ氏作『お田鶴』

築山殿事件の遠因?
瀬名がお田鶴の事を憐れんで、お田鶴の方の戦死の場所に百十株の椿を植えた事が「椿姫」伝承の始まりと言われています。
瀬名は、お田鶴が城主であった浜松城(引間城から改名)への移転を拒み、岡崎城に残ります。この理由は、明らかではありませんが、一説によるとお田鶴が亡くなった地である浜松に住むのは気が進まなかった、という説もあります。
これにより、夫婦別居となる訳ですが、家康と瀬名の間のコミュニケーションに支障が出て行き違いが生まれた可能性もあります。
スポンサーリンク
武田信玄の外交
密約は有った?
「どうする家康」では、徳川家康と武田信玄との間に所謂「国分協定(今川領を東西に分割し東部を武田氏が、西部を徳川氏が切り取るとするもの)」があったという説がとられていました。
国分協定が実際に有ろうが無かろうが、今川領の東側が武田領に、西側が徳川領になることは自明の理ですけどね
どさくさに武田軍の一部である秋山虎繁が遠江に進軍した際に、家康が信玄に抗議して信玄が謝罪。秋山虎繁を遠江から退かせています。そして、家康は信玄に誓詞を提出し、信玄は家康に血判状を提出しています。これらの傍証から国分協定は”実質有った”というのが可能性は高そうです。
信玄の駿河侵攻への流れ
- STEP011565年9月四男武田勝頼の正室に織田信長の姪を迎え入れ甲尾同盟締結
- STEP021567年10月武田義信事件が発生。義信廃嫡。
- STEP031567年今川氏真、甲斐への「塩止め」を実施
- STEP041567年11月義信の正室嶺松院が駿府へ送還
- STEP051568年徳川との同盟締結。信玄の駿河侵攻開始
同盟と言っても、「不戦同盟」のようなものでお互いに敵対しない、という程度のものでした。元々信濃と美濃の国境付近を領地とする武田方の国人と美濃の斎藤家が対立しており、武田信玄も味方してくれる国人たちの領地を安堵している以上、美濃の斎藤家と敵対するより手はなかった状況でした。そうした中で、織田家と事を構えるのは得策ではないという判断で、甲尾同盟に至ったと考えられます。
国人たちは、家臣では無く独立性が高いので、いつ敵方に寝返るかわかりませんからね。
武田信玄の外交政策の錯綜は、家臣団の独立性の高さも一因
織田信長の思惑
同盟を結んだ1565年は美濃攻めの真っ最中なので、美濃攻めを盤石にするためでしょう。信長が美濃を制圧したのは1567年です。美濃の西側の浅井と、東側の武田の両方と婚姻政策で同盟を結んで、美濃の斎藤家を孤立させてます。
美濃攻めの為に、美濃の西側の浅井と東側の武田と同盟を結ぶ信長。合理主義者の真骨頂か
バトルロイヤルの必勝法ですね。戦国時代の戦略は、誰とどういう順番で戦うかと言うことに尽きると思います。信長はそれが上手く行って、信玄は今一つ上手く行かなかったというのが結果に出ています。
スポンサーリンク
敵に塩を送る
信長と同盟を結んで、今川家と縁戚の義信を廃嫡にした信玄に対して、氏真がやった”経済制裁”ですね。北条家と組んで甲斐に塩が入らないようにしました。これに対して、謙信が甲斐に塩を送ったという話があります。
「塩止め」自体は実際にありました。「敵に塩を送る」は、武田家側の史料に出てくる話ですよね。上杉側の史料には、謙信が、「困っている甲斐に(価格をつり上げずに)適正価格で塩を売るように」と商人たちに指示をした、という史料があります。これが大きくなったのでしょうね。
武田方の史料:謙信が塩を送ってくれた
上杉方の史料:「困っている甲斐に(価格をつり上げずに)適正価格で塩を売るように」と商人たちに指示をした
謙信が武田に融和的だった理由
京での室町幕府13第将軍足利義輝暗殺が大きかったのでしょう。謙信は実はこの時期、輝虎と名乗っていました。”輝”の字は、足利義輝からの偏諱です。上杉謙信と足利義輝は仲が良かったようです。足利義輝は謙信に上洛して欲しくて、度々、上杉と北条・武田の仲を取り持とうとしていたようです。その為、謙信もいつまでも武田と揉めていないで、早く西に向かいたかったのだと思います。
徳川三河守藤原家康
徳川ではなく得川だった!?
家康は、祖父が”世良田”を称していたことや古い系図の”空白”を利用して、源姓になろうとします。そこで”得川”の姓を横領する事を思いつきますが、そのまま利用はせずに”得川”を”徳川”に変更します。
”得川”は史書によって、”得川”・”得河”・”徳川”と表記がまちまちだったので、一番見栄えの良い”徳川”を選んだものと考えられます
なぜ”藤原”?
改姓を認めてもらうのと、三河守になるためです。朝廷は前例の無い事は認めたがらないのですが、家康から依頼を受けた近衛前久などが、家康が主張する世良田の家系の中に藤原氏に改姓した前例があることを利用して、家康個人が”徳川”姓に変更する事を朝廷に認めてもらいました。
ただ、家康個人だけが改姓になった事は一族や家臣団の統制に副次効果もありました。
徳川に改姓したのは家康個人で他の一族は松平のまま。
スポンサーリンク
ネタバレコーナー
今川氏真のその後
そうなんですが、今川家自体は江戸時代も続くんですよね、高家として。
北条家の庇護を受けますが、武田と北条が同盟を結んだあと、家康の庇護を受けるようですね。
氏真と家康の面白い話
氏真も結構長生きで、没年が家康と1年違いですよね。家康と同じ75歳で亡くなる訳ですが、両者の間には面白い逸話が合って、晩年、氏真がよく家康の元を訪れると、きまって長話をするようになるそうです。氏真の長話に辟易した家康が、江戸城から離れた品川の地に氏真の屋敷を与えたというものです。